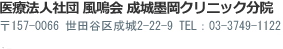成城墨岡クリニックによるブログ形式の情報ページです。
2011年04月15日
カテゴリー:院長より
見果てぬ夢の地平を透視するものへ-56-
朔太郎の、とりわけ詩集『青猫』の描き出す憂うつを基調とした表現世界は一体何ものの投影なのであろうか。
私は、これらの詩が、朔太郎が遂には自我の同一性にまで沈降させた<自己愛>の屈折した映像にほかならないと考える。
<自己愛>とはもともと厳しい内的な実体感によってささえられているものであり、それはまず母性との関係の内に定位されるものであるはずである。
母が私を愛するように、私は私を愛する、のである。
朔太郎が『青猫』を書き綴った時代は、朔太郎の最も激しい心理的動揺が認められる時代であった。それは、自分自身が内的にも、外的(主に経済的な問題として)にも父親から自立を強要されていた頃だった。無意識的な母親との心的共生状態と鋭く対比するものとして、父親の超自我が存在しはじめたのである。朔太郎のなかで非常に強固なものであったはずの生命の実体感=存在感が、それによって大きく崩れ去ったのである。
こうした「心的外傷」が、朔太郎の自我を一定の方向へと大きく動揺させ、同時に詩的な表現として朔太郎自身もその由来を明らかに出来なかった憂うつ性を導き出していったのではないだろうか。
朔太郎はやはりまぎれもなく「存在の悲しみ」を唄う詩人であったのだ。
そして、その存在は、遠く母親の実体感へと結びつくのである。
「穴」について、ウィニコットは、「乳房をむさぼり吸うことによって無を創造することだ。」と述べた。
僕等はたよりない子供だから
僕等のあはれな感触では
わずかな現はれた物しか見えはしない。
僕等は遙かの丘の向うで
ひろびろとした自然に住んでる
かくれた万象の密語をきき
見えない生き物の動作をかんじた。
僕等は電光の森かげから
夕闇のくる地平の方から
煙の淡じろい影のやうで
しだいにちかづく巨像をおぼえた
なにかの妖しい相貌に見える
魔物の迫れる恐れをかんじた。
おとなの知らない稀有の言葉で
自然は僕等をおびやかした
僕等は葦のやうにふるへながら
さびしいこう野に泣きさけんだ
「お母ああさん! お母ああさん!」 (「自然の背後に隠れて居る」)
(Ⅰ詩人論/朔太郎の内的世界つづく…)