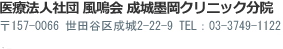成城墨岡クリニックによるブログ形式の情報ページです。
2014年04月25日
カテゴリー:院長より
見果てぬ夢の地平を透視するものへ-107
所謂ネオ・リアリズム以後の映画作品は、映画作品のもつ象徴化の過程と真向うから対立する形でリアリズムそのものを表現の強力な武器としてきた。だがもともとリアリズムというのは映画を≪見る≫側にとっては単に認識作用を軸とした表象化現象にその根拠を置いている訳で、考えてみれば私達は一つの映画表現の息吹きに直接触れるためにはいかにも疎遠な道をたどらなければならなかった。
だが、ロマン・ポルノなどの一連の作品はまさに映像のダイナミックスそのものであって、表現への意志というものが一種の心的緊張状態として映画の核をささえているのである。いうなれば一カット一カットをつなぎとめる強固な論理性も感覚もそれほど重要な契機である訳ではなく、カット割りの裏側にあるものは心的機制による状況作りである。
ロマン・ポルノに対する権力の取締りなどというものは、従って問題にならないほど表在レベルでのことであって、表現としての映画について本質的には何の関わりもない。
「意識に属する(知覚の)内容と(知覚の)対象との区別から、意識についての一般的本質洞察が得られる。」とビンスワンガーは語ったが、私がいま組みたてようとしている現代日本映画の存在論みたいなものについて触れようとするとき、かならず思いだすのはビンスワンガーの次の言葉である。
「われわれの知覚するのは感覚ではなくて対象である。しかし知覚された対象は知覚の中に含まれるのではなくて、われわれは知覚することにおいて対象へと方向づけられ『知覚という様態において』自己を対象に関係づけるのである。」(『現象学的人間学』)
(Ⅲ映画論/映画・表現・詩 つづく…)
2014年03月13日
カテゴリー:院長より
見果てぬ夢の地平を透視するものへ-106
「視覚は思考の一様態とか自己への現前ではない。それは、私が私自身から不在となり、存在の烈開――私が私自身に閉じこもるのは、その極限においてでしかないのだ――に内側から立ち会うために贈られた手段なのである。」(メルロ・ポンティ『眼と精神』)と述べたのはメルロ・ポンティだった。
例えば私は今、かつての日活ロマン・ポルノの一連の作品を想いうかべている。そこには藤田敏八があり、神代辰巳があり、村川透があり、田中登があり、それは同時に映画表現の現代における可能性の豊かな脈絡があった。
日活ロマン・ポルノを作品論としてとらえることはあまり意味がない。これらの作品は、映画表現の激しいダイナミックスのなかから生まれてきたものである以上、私達もまたその泥くさい葛藤の中へドップリとのめり込んでいかなければならないのだ。
ところで、見田宗介は「まなざしの地獄」の中で
「N・Nは異常なまでの映画好きであった。彼が幼時をすごした家の向いにたまたま映画館があったということもあろうが、それよりも映画というものが、ベニヤ板の穴がそうであったように、魂を存在から遊離させるものであったからではないだろうか。」
「覗くこと。夢見ること。魂を遊離させること。それはなるほど、出口のない現実からの『逃避』であるかもしれないけれども、同時にそれは、少なくとも自己を一つの欠如として意識させるもの、現実を一つの欠如として開示するものである。」
映画について触れられた言葉としてこれは非常に示唆に富んでいる。だが、ロマン・ポルノの作品のいくつかは純粋に映画に関するこうした概念化を突き破ってしまっていると言わねばならない。例えば藤田敏八の「八月はエロスの匂い」ではデパートのレジを襲ったやぶ睨みの少年は、おそらくは多くの
永山則夫を描いた新藤兼人の「裸の十七才」のリアリズムなどではとうてい及びつかない内的体験の表象を可能としているものは一体何なのだろうか。
(Ⅲ映画論/映画・表現・詩 つづく…)
2014年02月20日
カテゴリー:院長より
見果てぬ夢の地平を透視するものへ-105
「叛軍」製作集団による映画「叛軍」のラストシーンは強烈である。
壁の前に若い男が立つ。
「男Aに扮することをやめる。男Bに扮することをやめる。そしてなにものにも扮することをやめる。それで“私自身”と呼ばれるものがあとに残ったわけではない。さらに私は扮し続けてゆく。なにものにも扮することをやめ、なお私は扮し続ける。扮し続ける私を“私自身”と呼ぶことはできない。そして私は、“私自身”に扮している私、ですらない。私のうしろにも、“私自身”と呼ばれる私はいない。私のうしろで私はなにものでもない。ただ私がいる。扮している私がいる……。」
現在、映画における方法論について述べることはつまらない。方法論はすなわち表現論の中に暖く包みこまれてしまわれているのがいい。私達は例えば映画の中に何を見るか。俳優の演技の上手下手はどうでもよい。作品の評価などどうでもよい。単なる映画技術などもまたどうでもよい。
映画を作り出すという共同作業のなかで、作り出す側の交錯した意識が、どれだけ表現への意志となって突出していくかということを私は問題としたいのだ。
作品の解釈が幾重にも可能である映画こそ本質的な映画表現である、というときそれは映画を作り出す主体が中途半端なイメージをこねまわしているということではない。むしろ逆であって、それは表現の主体が強烈な自己主張を持っていることの当然の結果である。そこには、はじめから観客は観客として存在しない。同時に観客もまた表現の主体になり得るという遠い予感に安住している訳ではなく、観客もまた映画の作り出した状況によって、映画を造りあげていくものだという透明な認識がそこにはある。
(Ⅲ映画論/映画・表現・詩 つづく…)
2014年01月23日
カテゴリー:院長より
見果てぬ夢の地平を透視するものへ-104
Ⅲ映画論
私が映画に直接かかわっていた頃の論考であり、今では既に過去のものとなってしまった作業である。しかし、私は現在でも映画表現の可能性に私自身の夢をかけてみたい衝動にかられることがある。その意味でも、どうしてもこの本の中に収録しておきたかった。
時期を同じくして、同一の主題のもとに書きつらねたものなので、論理の重複もある。
「映画『旅の重さ』をめぐって」、「日活ロマンポルノの周辺」は、これも雑誌『詩学』に「私的表現考」の一部として連載したものである。
映画・表現・詩
映像表現を≪批評≫することによって、その表現の核に到達しようとするとき、私に与えられている方法論=認識論とは一体何なのだろうか。私が最も深く関心を持たざるを得ないのは、その表現の主体である人間の生き方であり、その人間が表現を提示しようとしている状況の構造である。
だが、その時私の映像表現を≪見る≫行為とは一体何なのだろうか。無論、私は既におぞましい状況の嵐の中に存在している。そして言うまでもなくその時点で、私は表現を夢みた人間達のあえぐような逼迫感をさぐりあてようとしている。だが、だからこそ私の≪見る≫行為の基盤とは何なのか。
既に今日、映画は≪批評≫としては成り立ち得ない場所にある。象徴論としての映画批評も、運動論としての映画批評も、技術論としてのそれも、もはや役に立たぬ遺物でしかないのだろう。
映画は、表現の一形態としても、観客の側にとっても無限の拡散現象をみせはじめている。意識の内部、知覚の内部に志向し未知なる経験の嵐をまきおこそうとしている。だからこそ映画は≪批評≫として成り立ち得ないのだ。しかし、そのとき私にとって映画を≪見る≫こととは何なのか。
(Ⅲ映画論/映画・表現・詩 つづく…)
2013年11月25日
カテゴリー:院長より
見果てぬ夢の地平を透視するものへ-103
このようにして、状況の内部に打ち込まれた個人的表現を、人間一般、あるいは大衆一般の表現へと志向させているものは、まぎれもない人間の真の連帯への意志であり、事象そのものに基いた私達の現象学的やさしさとでもいうべきものである。
何よりも事象そのものに志向し、事象そのものを了解する意志に裏づけられた、現象学的やさしさの存在なしにはすべての人間的表現活動は能動化され得ないだろうと私は思う。私達は幾多の分裂と、挫折とをくり返しながらこの現象学的やさしさを身につけていくことだろう。負けることを恐れてはならないのだ。それは多分、私達の問い続けていく生き方そのものに併行しているものであると私は考えるのだ。
そして、それらの営為のはるかかなたにあるべき、人間の真の連帯と新しい共同体の問題について、私達は現実そのものの認識と予感、そして日常での実践を背景にして、いずれ壮大な俯瞰図を描いていかなければならないものなのである。
(Ⅱ表現論/表現へ! 終)