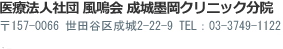成城墨岡クリニックによるブログ形式の情報ページです。
2010年12月24日
カテゴリー:院長より
見果てぬ夢の地平を透視するものへ-51-
おびただしいアフォリズムのなかで、朔太郎は幾度となく同じ題材をくり返しながら、自己の詩人である所以を書き綴ってみせる。それは、まさしく詩人としての自我同一性を客観として開示する方法の形態であったはずである。
だから、朔太郎は、結婚・母性・恋愛について言及しながら、また家・父について触れながら、朔太郎の立場とスタイルは常に辛辣でさっそうとしたものであり得たのである。
「すべての親たちは、真にその子供を愛してゐる。けれどもけっして同情はしない。彼のずつと幼ない子供に対して
も。または年頃の息子や娘に対しても。」(「愛の一形式」『虚妄の正義』)
「男と女とが、互いに相手を箒とし、味噌漉として、乳母車とし、貯金箱とし、ミシン機械とし、日用の勝手道具と
考える時、もはや必要から別れがたく、夫婦の実の愛情が生ずるのである。―――愛!あまりに巧利的な愛! (愛――
あまりに巧利的な)」(『同前』)
「想像力の消耗からも、人はその家庭を愛するやうになつてくる。」(「家庭的になる」『同前』)
「すべての家庭人は、人生の半ばをあきらめている。」(「家庭人」『同前』)
こうした表現の背後にある朔太郎の実生活について想いをめぐらすのはそれほど意味があることではない。
しかし、近代日本の自然主義文学に対する強い反抗をモチーフとして、朔太郎のアフォリズムが生まれたとしても、このように書きつけた詩人の内的世界の絶望的な孤独と、その孤独をおぎなおうとする強固な自我機能をここに認めることができるのである。
朔太郎は、同じ『虚妄の正義』のなかで次のようにも語るのである。
「人が家の中に住んでいるのは、地上の悲しい風景である。」(「家」)
そして、「港にて」には次のような表現もある。
「父といふ観念は、今日に於て一つの天刑観念である。この問題は、人間の最初の過失(原罪)が、何故に刑罰されね
ばならなかったかといふ、基督教のイロニックな神恩思想に於て、なるべく慈悲深く解釈されねばならない。」(「父」)
ここに語られるものもまた、「独りぼっちの虚無感と寂寥感」である。
(Ⅰ詩人論/朔太郎の内的世界つづく…)
2010年12月16日
カテゴリー:院長より
見果てぬ夢の地平を透視するものへ-50-
例えば、詩集『月に吠える』にみられる表現のスタイルをただ単に性的な感覚とか、生を病む姿だととらえるよりも、私はその中に朔太郎が意識せずして感じとっていた母親の抑圧からの独立を企図する激しい息づかいを感じるのである。
D・クーパーが述べたように、内的な家族(Internal Family)の抑圧から、母親の子供ではなく自分自身であることのイメージをみすえるためには、自分自身を<無>のなかになげいれていく行為が必要である。『月に吠える』が対象のない不気味な恐怖を唄えば唄うほど、朔太郎の表現行為は<無>の領域に近づいていくのである。
しかし、現実には朔太郎の生涯にわたる自我構造をきわめて規範的なものとして決定してしまったのもこの母親であったと言ってよい。朔太郎は、ただ単に溺愛されて育ったのではない、彼は本質的に「どのように生きるか」を母親から示されたことは一度もなかったのである。
吉本隆明は述べている。
「三十づらをしながら、母に寄食している生活上の無能者であり、不和な結婚者として家庭失格者であり、だれも仕事とも文学ともみとめてくれない詩人であるというようなさまざまな根がからみあったろうが、朔太郎の性的な感覚の特質が、思想的な意味をもとめて流れはじめたとき、たたかわずして挫折した生活のかげが、朔太郎のこころを占めるにいたった。」(「朔太郎の世界」)
詩集『月に吠える』から、『青猫』を経て『郷土望景詩』へ、そして『氷島』に至る朔太郎の詩的<完成>と、朔太郎自身が名付けた断章、「新散文詩」が「概念叙情詩」、「情調哲学」という呼称を経て、「断章」、「詩文風なる」へ、そして「アフォリズム」、「箴言」へと概念を変化させていく過程とは決して異質のものではない。
(Ⅰ詩人論/朔太郎の内的世界つづく…)
2010年12月05日
カテゴリー:院長より
見果てぬ夢の地平を透視するものへ-49-
「父の歩き方は、ふわふわと身体が宙に浮くような早足で、あやつり人形のようなぎごちなさだった。今にもころびそうで危ぶなかしくて見ていられないのである。祖母は夕方になると、『朔太郎がつまづくと危いから』といって、父の帰り道にころがっている大きな石ころをどけに行くことがよくあった。」(萩原葉子「折にふれての思い出」)
「……せかせかと足早に家に上ってくると、すぐに玄関にゆき着物とは似つかない汚れたソフトを頭に無造作にのせてでかけようとした。が、祖母が素早く見つけて、『今日はたしかに日を間違えないだろうね?天気予報じゃ今夜は雨だそうだから傘をもっておゆき』と父に新しい洋傘を持たせようとするのであった。傘は嫌いで必ずといっていいほど帰りまでに失くしてしまい、そのたびに祖母に叱言をいわれるので、『やめてくれ』というが、祖母はむりやりに父に押しつけて持たしてしまうのだった。
『買ったばかりだから電車や飲み屋に置いて来ては困るよ、それから幾度もいうけど着物は気をつけて汚ごさないようにおしよ』など、もう行ってしまった父の後姿にいい続けた。」(同前)
朔太郎自身がアフォリズムの中できわめて皮肉に、そして客観的に述べているような、<父>の存在とか、<結婚>とか<家庭>などというものは彼自身が目指した思想的表現のための辛辣な布石にすぎないのであって、現実には家族はいかなる形態においても単なる抽象物となり得ないのである。人は、まず家族体験のなかで孤独であることと他人と共にあることとの<弁証法>を認識するのであり、母子関係の持つ必要以上の共生から抜け出す孤独の場として家族の同一性は準備されていなければならない。
ところが、朔太郎の幼児期は、養育を一手にまかされた母ケイの溺愛によってつらぬかれたのであり、この傾向は生涯かわることがなかったのである。四十をすぎた朔太郎に対して、まるで幼児に対するごとくに注意をはらう母の姿は特徴的である。こうした母子関係から朔太郎は執拗に自分自身を岐立させようとする。朔太郎が、何回もくり返し子供の頃の夢について述べたり、無意識的な習性について語るのは母親の抑圧から自分自身をとき放つ意味も含まれていたにちがいない。
(Ⅰ詩人論/朔太郎の内的世界つづく…)
2010年11月18日
カテゴリー:院長より
見果てぬ夢の地平を透視するものへ-48-
朔太郎の生き方は、彼自身が蓋然的に規定してしまっていた芸術的野心=詩人という自我同一性へ、表現行為としても実生活においてもいかに自己を密着させるかという努力によってつらぬかれていたと私は考えざるを得ない。それは既に詩集『月に吠える』の時代からはぐくまれ、「もはや、人生にたいする青年の大半のイデアをうしなった」(吉本隆明)晩年に至るまで強固に持続したアイデンティティであった。
(現代において私達が日常遭遇する異端的な内的現象が、むしろ自我拡散(Identity diffusion)によって代表されるとき、朔太郎という近代の異端的自我が、強烈に詩人というアイデンティティを構築し、その同一化のなかでしか生きられなかったということは興味あることである。それは、近代と現代という日本の社会構造に対応した人間の内的現象の許容度にもよるはずである。)
朔太郎のこのような自我構造が、数々のエピソードとしての強迫行為を導き、時には朔太郎のナルシシズムの基盤となったということを想定することはそれほど困難なことではないと考えられる。
しかし、朔太郎の内的現象にとって最も重要なことは、朔太郎の幼児期の家族内関係と、なかでもとりわけ、母・子関係に注目することである。
朔太郎のおびただしいアフォリズムや、論評のなかで、彼の家族や母に対する具体的な関係を示唆するものはきわめて数少ない。にもかかわらず、私にはこのことを抜きにして朔太郎という人間を語ることはできないという気がするのである。
(Ⅰ詩人論/朔太郎の内的世界つづく…)
2010年07月10日
カテゴリー:院長より
見果てぬ夢の地平を透視するものへ-47-
白秋に対する同性愛とか、門を出るとき、いつも左の足からでないと踏み出せない=強迫行為とかが、ひとたび<人間的異常>の範疇にある言語で規定されると、それらは際限なく拡散し、見えもせず実体もない仮空の構造として朔太郎の世界を映し出すのである。このようにして、人間の表現行為がどんなに歪曲されてきたか私達は無数の例をあげることができる。それは単に、対象となる実現者を誤らせるだけではなく、人間の表現論そのものを誤らせるのである。
私がここで執拗にこのことをくり返すのは、実は朔太郎自身がこの種の呪縛から逃れてはいないということに触れたいためなのだ。
朔太郎自身が己に関して書き綴ったおびただしい異常性への傾倒は何を意味しているのだろうか。朔太郎の自我が持つ強大なデフェンス機構の解釈からだけでは、この答えは見出すことはできはしない。
「僕は昔から人嫌ひ、交際嫌ひで通ってゐた。しかし、それには色々の事情があつたのである。もちろんその事情の第一番は僕の孤独癖にもとづいて居り、全く先天的気質の問題だが、他にそれを余儀なくさせるところの環境的な事情も大いにあつたのである。元来かうした性癖の発芽は子供の時の我まま育ちにあるのだと思ふ。僕は比較的良家に生れ、子供の時に甘やかされて育つた為に、他人との社交について自己を抑制することが出来ないのである。その上僕の風変わりな性格が小学生時代から仲間の子供とちがつていたので、学校では一人だけ除けものにされ、いつも周囲から冷たい敵意で憎まれていた。」(「自叙伝覚え書」)
(Ⅰ詩人論/朔太郎の内的世界つづく…)