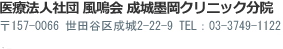成城墨岡クリニックによるブログ形式の情報ページです。
2008年07月30日
カテゴリー:院長より
見果てぬ夢の地平を透視するものへ-9-
スターリン死去にともなう特赦により、帰国した石原吉郎は「望郷と海」をこのようにしめくくる。だが現実には、石原吉郎の戦争は終っていなかった。「シベリヤ帰り」は、既に日本本土においても<棄民>でしかなかったのである。故国が<向う側>から迎えにくることによって終結するはずの「望郷」はついに、断ち切られたまま宙に浮いてしまう。職もなく、金もない。ラーゲリで石原吉郎が怒りと失意のなかで呟いたはずの「弦にかえる矢があってはならぬ。」ということを骨身から断言せざるを得ない状況であったであろう。石原吉郎の表現の始動が、「記憶の中にいっさいの倫理を置いて戦後の日本を生きようと決意」することにあったのも、あまりにも当然であった。石原吉郎が、失語について語るとき、現実に不在であったのは言葉そのものであったのではないということをこそ物語っているのだ。「自立」がその表現を求めて疼いているのだ。突きあげるような力動がそこには存在しているのだ。
私達は既にいかなる効果をも期待しない、と私は冒頭で述べた。私達は根拠を問われ続けているのだから。このとき、石原吉郎の『望郷と海』は豊かな内実を、持続する緊張に絡ませてまさしくこの場所に存在している。石原吉郎の表現には終りがない。輪郭もなければ希望もない。そこには無限に沈澱していく堅い意志があるだけである。そして、これが私達をとり囲んだ状況のすべてであると私は思う。
「少くともこのようなかしゃくない戦いが現に私達が生きている世界のなかでいとなまれているということ、そのような人たちが、私たちと時をおなじくしてこの地上に生きつづけていること、現に私たちがこうして希望をうしないつつある瞬間に、まさしくその人たちの希望のない戦いが、一歩の妥協もなく、執拗につづけられているということ、そのことこそ私たちの希望でなくてなんであろう。」
(「1959年から1962年までのノートから」)
石原吉郎の表現はしたたかである。(Ⅰ詩人論/『望郷と海』覚え書おわり)