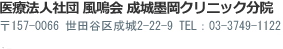成城墨岡クリニックによるブログ形式の情報ページです。
2015年02月06日
カテゴリー:院長より
見果てぬ夢の地平を透視するものへ-117
私が「旅の重さ」に触れ、世代の被表現性について思うとき、私の内部でいまだに風化しないでいるはずのこうした<行為>があとからあとから浮んでくる。それはいつも、息苦しい状況の壁に激しくぶつかり、いたずらに滅んでいくようにみえながら、その奥にきわめて重い真実を含んでいたのだ。
映画での少女の軌跡は、物語としていかにも単純なのだが、そのくわえこんだ内実というのは豊かなイメージと、この高橋洋子という新人のさわやかな肉体とにささえられて、観念を越えたところで切実な内容を描くことになった。かつて、私にとっての“青春映画”は大島渚の「日本春歌考」であり、黒木和雄の「とべない沈黙」であり、浦山桐郎の「私の棄てた女」であったのだが、いま、これらの映画の一種さえ、いかにもディレッタント的だと感じるのは何故なのだろうか。ここ数年の間に、何がおこったのだろうか。
黒木和雄の幻の名画「新宿で女をつくろう」について、シナリオの作者達は数年前にこう書いている。
「かつて地方からあこがれ東京に出てきた私達は、今では小説や芝居や映画をつくろうとしているわけですが、新宿という街はそのような私達と共にあります。新宿は失われた時を求めるに充分なカスバであり、その路上は過去への遡行であると、見えながら実は鮮血にいろどられた未来を準備するものであります。私達が新宿で女をつくることの大切さは、もう言うには及ばないことであります。」(内田栄一、清水邦夫、黒木和雄)
しかしこのいかにも未開の青春映画の中では、新宿で女をつくること=新宿という状況の中で主体性を確立することは遂に、突きあげてくる激しい情動を開花させることにはならなかったと言っていいだろう。新宿で主体性を確立するという実にカッコイイ図式に半ば酔いしれているとき、確実に新宿は風化し、背後にある黒い闇によって占拠されていった。いま新宿について語るとき、私は新宿を占拠された場所としか言いようがないのだ。
だから旅に出る、ということではない。またひとつ忘れられていく表現の過去を横切って、旅に出るということではない。居残って、居直って苦しく暮していく者もいるのだ。だが、私も旅に出たい。
(Ⅲ映画論/映画「旅の重さ」をめぐって つづく…)
2014年12月12日
カテゴリー:院長より
見果てぬ夢の地平を透視するものへ-116
「旅の重さ」の中では、早熟な、しかも実にきまじめにしか(涙が出るほど!)人生に対してもはや対峙していけない少女の眼を通して描かれる四国遍路や、旅芸人の共同社会、そして人情とか愚かさとか、いやらしさとか、ずるさとかおおよそ日本人のかもしだす存在感がそこここに投げ込まれていて、しかもそれが実に説得力を持っているのは何故なのだろうか。言葉を換えれば、そこここの現実が、なまじの論理など及ばない激しい認識を可能にしているのは何故なのだろうか。
大島渚の映画を、一つの対極として、私には映画の可能性の極が、ここにもあると思われるのだ。
この早熟な少女は、遍路のはてに小さな漁村で知りあった正体不明のヤクザな男(高橋悦史)の家に居ついて、彼と夫婦になってしまう。あらゆる機構の中で人間関係の巨大な風化が進んでいて、そのことに最も敏感である人々にとって現在を生きるということは、常にどうしようもなく自分の生き方を主体的に選びとること以外のなにものでもないだろう。“表現”と私達が言うとき、その“表現”もまたどうしようもなく主体的である。
「橋を、広場を、部屋を、かんたんに通りすぎるな。権力にも、寄生虫的な参加者にも視えない空間が存在するのだ。汝はなぜここにいるのか。もはや、ここから脱出することはできない。ここに集中してくる全てのテーマを一人でも生涯かけてひきずっていく力を獲得するまでは、何よりもまず、バリケードとか、占拠とか言う言葉を汝だけの言葉に変化させ、その方法の追求ないし総括の場が、そのまま闘争となるような場を創りださなければならない」(松下昇『情況への発言<あるいは>遠い夢』)
かつてこう語った松下昇のことを、私はまだ忘れていない。松下昇が書きなぐった、神戸大学教養部正門前の陸橋上の巨大な<>と、昭和四五年一月八日、神戸大学B棟一階一○八教室の黒板上の一二個の<>のこともそして、それ以後の松下昇の<行為>については私は忘れてはいない。
(Ⅲ映画論/映画「旅の重さ」をめぐって つづく…)
2014年11月10日
カテゴリー:院長より
見果てぬ夢の地平を透視するものへ-115
映画「旅の重さ」をめぐって
私はいま人間の表現と、表現行為についていくつかの角度から考えはじめている。それは<人間>というものをまともに、全存在的に含み込んだ壮大な見果てぬ夢だろうという予感がある。
ところで、私が表現の背後にどうしようもなく息づいているものとしてある<世代>というものについて語るとき、私は決して<世代論>について述べているのではない。時間軸によって区別されるべき世代というものを措定し、状況とのかかわりあい方を論じることはいうまでもなく不毛である。私の中で<世代>とは一つの踏絵であり<時代>に対する反意であり、どこまでも主体的なものである。
現在では私達を今なお包囲している状況の壁の前に、日常生活のみならず大学=学問も、個人の精神構造もみごとに退廃していく過程があり、その背後にきまって顔をのぞかせている鬼面は管理社会の演出者達である。
ところで、私はいま、新しい地平からの映画論ということを考えている訳だが、例えば、昨年の斉藤耕一の作品である「旅の重さ」はこのような世代の被表現性についてはっきりと主張した映画であった。
「旅の重さ」は一人の少女(高橋洋子)が生きていくことの重さ、生きつづけていくことの重さを求めて旅行をする。ただそれだけの映画であった。しかしそこには映画として豊かな問いの設定と、それを裏付ける確かな演出が存在していた。
斉藤耕一は単に映像派とか、青春映画とかいうレッテルで割り切れぬほど鋭い感性をもっていて、それ故に映画の奥底にうずくものは彼の鋭い感性と、それをささえ切れずにいる現在の日本映画界の桎梏なのだ。私にはそれが、斉藤耕一の映画を、映画として成功させているもののように思われるのだ。
(Ⅲ映画論/映画「旅の重さ」をめぐって つづく…)
2014年10月16日
カテゴリー:院長より
見果てぬ夢の地平を透視するものへ-114
言うまでもなく、藤田敏八の映画は一つの風俗として流れてしまうだろうという不安は常につきまとっているのだが、彼の作業を既に資本の側に収奪されている風俗とみるか、みないかということは、一つには藤田敏八自身とはまったく関係のないところで、少なくとも私達が、どのくらい、状況に対するいらだたしさと無念さを抱いているかということにかかっているのではないだろうか。その時にこそ、既に私の中で映像は単なる一般論としての驚きを超えているといえるだろう。
最後に、私は実にわかりきった問題を藤田敏八自身に語らせてみたいと思っているということを記しておく。
「甘ったれるんじゃねえ……。てめえの牙はてめえで磨け」(若者の砦)
と語る藤田敏八に。
「N・Nが現実に穴をうかがったのは、N・Nとおなじく体制の弱者であり犠牲者である。年若いガードマンと運転手たちと、七〇歳に近い神社の夜警員との、四つの生きている頭骸骨にすぎなかった。
N・Nの弾道がまさにその至近距離の対象に命中した瞬間、N・Nの弾道はじつは永久にその対象を外れてしまった。ここに体制の恐るべき陥穽はあった。」(「まなざしの地獄」)
という三田宗介の言葉に代表される内実を!
(Ⅲ映画論/「赤い鳥逃げた」=藤田敏八 終わり)
2014年09月13日
カテゴリー:院長より
見果てぬ夢の地平を透視するものへ-113
かつて、70年を数年後にひかえた当時、私の友人はいつも口ずさんでいたものだ。
≪日本映画とやるときにゃ ホイ
命かけかけせにゃならぬ ホイホイ≫
黒木和雄の「新宿で女をつくろう」は、主体性の確立という困難な命題をかかげながらその作品を次のようにしめくくった。
土工と穴の中で抱きあいながら
土工「新宿でも穴を掘れるぜ」
ノコ「………」
土工「新宿で穴を掘ったら?」
ノコ「そうね」
土工「おれも、新宿で女を作るから」
ノコ「え?」
土工「新宿であんたとね」
ノコ「ああ、一緒に住むのはいやだけど、一緒に住まなくても……」
土工「どこでも会えるさ、こうやってね。」
ノコ「(うなづいて)一緒に住まなくても暮らして行けるわね。」
土工「おれ、いろんなところ渡り歩いてきたけど、やっと新宿でねえ……新宿で女を作れるようになったぜ!見通しゃ明るいや!」
いま「赤い鳥逃げた」の主人公達の掘った穴は、このような予感からは生まれるべくもない呪縛にがんじがらめにされている。生きるということが単に、青春の仮借なさを借りて語られている訳ではないのだ。
(Ⅲ映画論/「赤い鳥逃げた」=藤田敏八 つづく…)