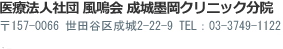成城墨岡クリニックによるブログ形式の情報ページです。
2015年08月22日
カテゴリー:院長より
見果てぬ夢の地平を透視するものへ-122
藤田敏八ばかりを例にとる訳ではないが、彼の「八月の濡れた砂」、「八月はエロスの匂い」、「エロスの誘惑」、「赤い鳥逃げた」というロマン・ポルノ以外の作品をも含めてながめてみると、やはり「八月の濡れた砂」が佳作であることは、はっきりしている。映像の持つ表象像からすれば、「八月の濡れた砂」の中の少女テレサは忘れがたい存在であった。だが、私がどうしても気になるのは「八月はエロスの匂い」の中のやぶ睨みの少年のことである。彼はデパートのレジを襲い、金を奪って逃げた、暗い影を持った少年である。社会からドロップアウトした彼の仲間の中でもシラミと呼ばれさげすまされている少年である。彼の抑圧そのものが、「八月はエロスの匂い」のテーマであった。映画の主人公は、この少年に掌を刺されながらも、少年の存在自体が気になり出していくデパートガールなのだが、いつからか、映画はすべてが少年の抑圧の構造を解析することになってしまう。
私達は、かつてのおびただしい闘いの中で数多くの犠牲者を出してきた。だからこそ、私達自身が犠牲者だというような語りには顔をそむけたくなるのだ。だが藤田敏八を含めてロマン・ポルノに描かれる青春像には不思議なやさしさが満ちている。そのやさしさの由来こそが、映画表現のダイナミクスの中核であるように私には思える。
ロマン・ポルノは大上段にかまえて状況を描き出す訳ではない。感動的な物語が展開する訳ではない。一時間一五分、制作費八百万円のカラーワイド映画は、いかにも貧弱でさえある。
だが、そこに映画表現にとってまったく新しい渦潮が存在していたこと、それは事実なのである。
「報復は最終的には一行の詩を書かせることではないかと或るとき、ふっと思ったのです。相手をなぐることでもなければ、殺すことでもない。或る情況に原罪性をもってかかわっている全ての人達が一行の詩をかかざるを得ないような現実的条件を作り出す、それが本当の報復になるであろうと思います。」(松下昇『私の自主講座運動』)
(Ⅲ映画論/日活ロマン・ポルノの周辺 終わり)
2015年07月06日
カテゴリー:院長より
見果てぬ夢の地平を透視するものへ-121
ミシエル・フーコーは彼の著作『狂気の歴史』に触れて次のように書いたことがある。
「『狂気の歴史』やその他のところで示そうと試みたのは言語表現の形式や概念や制度や慣行などを相互に結びつけている組織性というものは、(忘れられ、被いかくされ、それ自体から外らされた)根本的なある思想だとかフロイト的なある無意識などの領域に属するものではなく、それなりの特殊な形式と規制をそなえた、知識の無意識というものが存在するということなのである。
つまりわたしは、知識の領域において生じうるが、いわゆる“進歩”の一般的な法則にも、ある始まりの反復というものにも還元することのできないそうしたもろもろの出来事というものを研究し分析しようと努めたのである」「(『デリダへの回答』)
ミシエル・フーコーが「知識の無意識」と述べたものは、いわば≪狂気の復権≫を裏側から位置づける遠い予感であり、人間の文化状況のなかに見すえられた厳しいダイナミクスそのものだったのだ。
だから私は、現在の映画表現について触れる時「いわゆる“進歩”の一般的な法則にも、ある始まりの反復というものにも還元することのできないそうしたもろもろの出来事」を対象とせずにはおれないのだ。その背後には映画という素晴らしい表現手段が、単に個人における知覚現象、表象現象といった狭い領域で象徴主義的に、あるいは運動論的に批評されることへの反発があると言ってよいだろう。
その意味でロマン・ポルノはいま始まったばかりなのである。
(Ⅲ映画論/日活ロマン・ポルノの周辺 つづく…)
2015年04月25日
カテゴリー:院長より
見果てぬ夢の地平を透視するものへ-120
ところで、表現行為論からすれば、あらゆる表現行為は、その表現主体における社会的背景とは無関係ではあり得ない。
と、すれば、実に裁判の席上で裁かれなければならないものは一体何なのであろう。それは単に一カット一カットにおけるワイセツな描写などという個々の<行為>では絶対に無いはずである。
不思議に私は思い出す。一九七〇年を前にして、あらゆる新しい闘争の場で問われていたのは、実はこの問題だったのだ。何故に、東大闘争裁判その他において分離公判が反対されてきたかということの意味も、ここに存在するのだ。<行為>そのものを裁くということは相手が人間である以上、それはその社会的背景を裁くということ以外の何ものでもないのである。例えばそこで、分離公判の法的論理根拠である刑法学者の言うところの「構成要件」というのは単に、暴力行為とか不法行為とかの有無を条件にしているのではないことを、私達はもう一度確認しておかなければならない。
だが、ここに問題はもう一つある。それは、個人の表現行為は本来自由であるべきであって、それを裁くことは出来ないという大原則である。
同じく重要な憲法上の公理であった思想の自由は、その思想の自由そのものを裁くものとして登場した戦前の治安維持法、国防保安法、戦後における破防法、国家公務員法、地方公務員法などの法律によって厳しく否定されてきた。例えばそれは、厳密に思想の問題であった煽動というものに対しても、大きな罰則をつけ加えて、ブレーキの役目をはたさせる法律でもあったのである。ある一定の、非客観的で些細な、つまりあらゆる意味で科学的でもなく人間的でもない一定の条件の下で、憲法上の誇るべき大原則が突然に犯罪にと変化するという驚くべき逆説を、国家はいとも簡単に既成事実としてしまったのである。
いま、この二の舞いが表現行為というものを軸として確実に行われようとしているのである。
≪犯罪≫というものに対する徹底的なシンパシーが藤田敏八や神代辰巳等の映画の必要な構造となっているのも、表現のダイナミクスにとって、また現在における個々人の個別的体験にとって、このような社会規範がいかに権力的で曖昧なものであるかということを示しているのだ。
(Ⅲ映画論/日活ロマン・ポルノの周辺 つづく…)
2015年03月26日
カテゴリー:院長より
見果てぬ夢の地平を透視するものへ-119
そこでは、映像表現の主体となるべき共同体が存在し、その共同体を構成するはずの個別体験によって提示され、あるいは引き裂かれた葛藤が強烈な表現への意志を背景にしてある未完成な映像的状況を作りあげていたのだ。まず確認しておかなければならないのは、もともとこのような映像表現はポルノなどとは無関係に、現在の映画というものをめぐる状況によって規定されていたということである。しかし、このような新しい表現の形が、真先にポルノとして突出してあるということも同時に興味深い事なのだ。例えば、神代辰巳の「濡れた欲情」や「濡れた唇」では、そのダイナミクスは本来ポルノなどという言葉とは無関係な緊張状態と切実さを含んでいた。
もともと日本映画はここ数年間実に非生産的な場所へと、苦々しくも追いやられてきていたのだった。
かつてのロマン・ポルノでさえも、一つの運動としてそれをとらえることは不可能であるし、表言論としてもいまだ荒削りな実験である。それにもかかわらず、神代辰巳や藤田敏八や村田透等の息吹きが新鮮であるかのように見えるのは、彼等には映画を作ることがすなわち一つの状況を作り出すことだという確信があるからであろうと私は思う。
だが、現在このロマン・ポルノは現実に、表現の問題として論じられるよりも以前に、取締りを強化され、被告として裁かれているのだ。このことについて触れる前に私には一つだけはっきりとしておきたいことがある。それはロマン・ポルノが権力によって被告の場にあるということを私は表現行為論ということから問題としたいのであって、映画をめぐる表現の問題として考えているのではない。何故なら、現在のロマン・ポルノにとって、ポルノであるということは絶対的な必要条件ではないと私は考えているからである。映画におけるこの新しい波は今後、あらゆる形態の中に内在化される豊かな可能性を持っているのだ。
(Ⅲ映画論/日活ロマン・ポルノの周辺 つづく…)
2015年03月01日
カテゴリー:院長より
見果てぬ夢の地平を透視するものへ-118
「旅の重さ」の少女は、四国遍路の旅に出ていく。どこかの巨大資本のように、日本発見が目的ではない。過去からの人間の悲しみの重積であり、旅がじかに“表現”であるはずの、四国へ。
この少女の心の振子は、激しい振動を持ちながら、ぎりぎりまでせん細な糸によって営まれている。糸が切れるまでに、なんとか自分の生存していける“場所”を見出さねばならない。むこうからやってくる“場所”は簡単でも、こちらから、内側から求めていく“場所”は困難である。
斉藤耕一はなかば恥じらいながら、居直っているのだと思う。四国の自然を追うカメラの動作の中にそれがにじみ出ている。そして、こうした風景の中に、この肉体だけはきわめて健康でありながら、どこか決定的に場ちがいな感覚を持った一人の少女を、ポンと放り出してみる。それが演出というものだろう。
日本映画の新しい世代は、その表現における仮借ない論理性であり、豊かな感受性に裏付けられた鋭利な眼である。
日活ロマン・ポルノの周辺
映画についての表現論を続けたいと思う。
私は例えばかつての日活ロマン・ポルノを映像のダイナミクスの内にとらえるべきものであって、個々の作品論として批評することは出来ないと考えていた。
(Ⅲ映画論/日活ロマン・ポルノの周辺 つづく…)