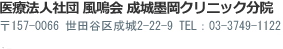成城墨岡クリニックによるブログ形式の情報ページです。
2016年03月13日
カテゴリー:院長より
見果てぬ夢の地平を透視するものへ-132
ii
<私が書く>という現象は一体どんな意味を持ち得るのか。<あなたが詩を書く>のは何故なのか。
背後からせきたてる陰の声、状況のなかでついに未完のまま拡散していってしまう厖大な意志に支えられて、一個人の現象が表現として定着していくのだろうか。
それにしても、人間の表現行為について、また人間の精神現象について、何故こんなにもおびただしい書物が書かれ、多くの体系が企図されようとするのだろうか。
そこに病める人間がいるから、などという解答を私は絶対に認めることはできない。現在の表現行為論も、精神現象学も決定的に正常者の側に収奪されており、さらにはより完璧な比喩のようにいずれは巨大な権力の懐におさまってしまう性質のものである限り、私はそれらの解釈を私のものとして肯定することは出来ないのである。
何よりも、なお一層人間的な生き方を中心課題としながら、学問とは一体何かということをもっともっと単純な地平に持ち込んで問いなおすべきなのだ。そして、そのためにまず私達が日常のなかで行っている諸行為の意味性をたずねあてていかなければならない。職業とは何か。生活とは何か。怒り、悲しみ、快楽、絶望、不安、こうした心理的機制さえも私達は再び問いなおす必要にせまられている。
「男達は家にいる女達の為に働いている。自分の為の働いてくれる者を持っているとは何と凄いことだろうと思う。その何でもない世界、それが私達は欲しいのです。
たとえ夕方には病院に戻らねばならないとしても、一ときでも人間らしい生活を味わってみたいと思います」(小林美代子『髪の花』)
(Ⅳ私的表現考/表現の現象学 つづく・・・)
2016年02月12日
カテゴリー:院長より
見果てぬ夢の地平を透視するものへ-131
このような江藤淳の言葉には、安価な権威に安住したままスッポリと人間を脱落させてしまった批評家の悲しい姿がある。江藤淳がこのように語るとき、江藤淳そのものの生きかたの基盤を私は見つめたいと思う。一つ一つ反論するのも腹が立つし、私は小林美代子の表現を全く別の地平から眺めようとしているのだから。
「恥かしさと再発の恐ろしさに下着の下を冷汗が流れた。
この状態があと一日つづいたら、自分が判らなくならないうちに、自分から、あの精神病院の檻の中に閉じ込めて貰いに行かなくてはならない。嫌だとか、窮屈だとか言っていられない。他人に迷惑をかけたり、自分の家を台なしにしてはいけない。帰ってくる所がなくなるからだ。いや家があっても恐らく兄弟は、今度は一生病院に置くだろう。それでも行かなくてはならない」(蝕まれた虹)
小林美代子の作品を不合理な流通の場にひきずり出し、遂に“狂気の才女”としてしか批評できなかった<状況>の側は、もはやこのような質の文学を手にすることは出来ないだろう。
そして、私がさらに小林美代子の表現について、敢えて状況的につけ加えるなら、小林美代子の死は48年度に企画され、みじめな失敗に終った、厚生省の精神衛生実態調査の実施の問題と不可分のものであった。
(Ⅳ私的表現考/表現の現象学 つづく・・・)
2016年01月12日
カテゴリー:院長より
見果てぬ夢の地平を透視するものへ-130
同人誌「文芸首都」において、はじめて小林美代子の小説に出会ってから、昭和四六年度群像新人賞を得た「髪の花」、そして遺稿である「蝕まれた虹」までの作品に接してみると、これはやはり死ぬべくして死んでいった人間の、他にどのようにも図式化できない命の記録であるように私には思えるのだ。
小林美代子の内で、自我の崩壊をかろうじてくいとめていた書くこと、表現することへの意志は私達にあらためて、表現行為の持つ人間的意味の中核をあきらかにしてくれる。小林美代子の描き出す世界は、おそらく表現論の故郷である。だから、それは本質的に内在的、存在論的な表現の形であるとも言えるのだ。だが、私達が自己の生存の問題について触れるとき、単に小林美代子の作品をこのように位置付けることが私達にとってどのような意味を持つものであるのだろうか。私達が、そもそも作品を位置付けるということは一体何なのか。私達の表現行為は一体何なのだろうか。
ここで、私は一つのことを言いたい。小林美代子の表現行為をささえていた自我の崩壊はとてつもなく内的な事実であることは確かであり、この内的な存在にむかって私達の表現論は突出していかなければならないことも事実である。だがしかし、小林美代子の死はどのようにしても小林美代子の死を拒絶することができなかった<状況>の側の責任であると私は思う。
かつて、江藤淳は群像新人賞の選評で次のように語っていた。
「近頃では、狂人のほうが正常人より純粋だとか、むしろ現代社会の“歪み”が狂人によって告発されているのだというような言説をなす者が、専門の精神科医のなかにさえときおり見受けられる。インテリの寝言とはこのことであって、こういう曲学阿世のともがらは、狂人のなかにひそむ治りたい願望について、一滴の涙すら注ぐことができないのである。単なる安価なヒューマニタリアニズムでこの涙を流すことができないのは、それにもかかわらず狂気というものがはなはだ治りにくいものだからである」(『髪の花』を推す)
(Ⅳ私的表現考/表現の現象学 つづく・・・)
2015年12月26日
カテゴリー:院長より
見果てぬ夢の地平を透視するものへ-129
正常な世界に不満を持つほど、私は正常な人間ではない。どんなに最低の正気でも、狂うよりはましだ。」(小林美代子『蝕まれた虹』)
小林美代子の死が知らされたのは、昭和四八年九月一日だった。死後二週間を経て、三鷹市の自宅で発見された小林美代子の孤独で、いたいたしい死のことについて、私は本来なら何も語るべき言葉を持たない。だが、小林美代子の死には、一人の人間がどのようにも支えきれなかった巨大な設問が宙ずりになっているのだと私は思う。誰もが、問題にすべきであるはずなのに、誰もが、まずはじめにさけていってしまう、表現と状況の壁のことである。
小林美代子の文学的行為は、決して概念的な規範のなかで裁断されるべきものではない。狂気とか、批評とか、完成とか、それらもろもろの商標こそ、実は小林美代子の生をおびやかし、表現の核を砕き割った加害の構造である。
小林美代子の作品は、何故書くか、何故書くかという自らの問いを一方の極点としながら、もう一方の極点では、この問いを発しながら、この問いそのものを支えている自我の存在を見きわめることをもう一つの課題とした二重構造として成立している。
小林美代子の文学はいたましく、おぞましい。だが、そのことは、既に小林美代子という人間の生が個々人の感受性の埒外のものとしていたましいものであったからにほかならない。
自我の存在を見きわめるということが、小林美代子の作品の跳躍の契機となっているというとき、それはこの対極として小林美代子の内部では既に自我が鋭く脅かされている状態にあることを予感している。
「ほとんど睡眠薬で眠っている。睡眠薬の眠りは、黒い鉄板でガッと思考を断ち切ったような闇の、全く自己のない眠りである。電話が鳴りつづけていたような気がする。不意に大きくベルがなる。(中略)
私は電話に引きつけられてしまう。電話の小さい穴から、それが私の責任のように聞える。
また下痢症状が起り始めた。世の人の不幸の責任は全部私にあるように思い始める。電話を放すことは、あちらを放り出すことになる。じりじり握りしめている。私は早くころりと眠りたいと思う。」(蝕まれた虹)
(Ⅳ私的表現考/表現の現象学 つづく・・・)
2015年12月01日
カテゴリー:院長より
見果てぬ夢の地平を透視するものへ-128
だが、私がこの表現考のなかで把えようとしている現象学的叙述は、いわばこの確固とした体系、そして至るところの判断中止(=アポケー)を包含しているものではない。私の内で現象学は常に「混沌そのものへ」むかう。すなわち、人間の最も否体系的な、否外在的な、そして被表現的な存在の激しい象徴である。
だから、この現象学そのものは必然的に、私達が<状況>と呼びならわしている、社会人間的構造のなかに突出していかざるを得ないのだ。
私達が真に人間的な生存を企図する場合、そしてこの企図のもとに生きながらえるためには、その前に私達が果し得るべき跳躍が措定されなければならない。そして、この跳躍のための準備段階として個人に内在されているものが<表現>そのものであると言ってよいだろう。そして、その<表現>をめぐる解釈学の試みが、私が現象学的叙述と呼ぶところのものなのである。
私がなぜ、人間の表現行為を、おしなべて必要以上に問題としようとするのかは、個人の内面の問題として疎外され、さらに、個人の外在的関係としてとして疎外されるという二重構造に包まれてしまっている、現在の私達の自我の息ぐるしいまでの心のあえぎを、どうしても消し去ってしまってはならないものだと考えるからである。
例えば、私達は実に多くの、私達に関係づけられた人間の死によって私達の実存を規定されている。それらの死は、単に状況のなかでの殉死者達のみを意味するものではない。私達の感性が触れ、私達の生存に深くかかわりあう、至るところの死者達である。
「昼から電燈をつけて毎日向った机、沢山の言葉が浮び、消され、書かれていった。時に絶望し、焦慮し、虚脱感に襲われた。メニエール氏病の目まい止めの薬と水の入ったコップを机に置いて、発作に備えたりした。
その絶望もここでは王冠のように輝いていた。
私の影となった、正気の自分が、そこ、ここで、飯を炊き、机上で、抱かれた処女のようなはじらいと期待で、文章の生まれるのを庭の椿に目を放って待ち、床に座って眠る為のブドー酒を含んでいる。
(Ⅳ私的表現考/表現の現象学 つづく・・・)